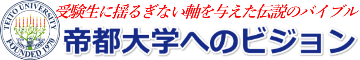別冊『子育て18切符:学習の本質発 モンテッソーリ経由 ロマン行』の中で『離す?離さない?』と題して『子育て四訓』を素材にお話をさせていただきましたが、今回はその続編として少し補足的にしたためたいと思います。
オーストラリア/メルボルン大学の臨床心理学者で子育てに関して世界的に影響力のある著作を書かれているスチーヴ・ビダルフという方が居られます。
例えば日本でも翻訳されている『男の子って、どうしてこうなの?』を見ますと、男の子の脳と女の子の脳は違うという理論と男性ホルモンであるテストステロンの作用を軸に、特に男の子の子育てにとっての方法論が展開されていきます。
所謂、男性脳と女性脳という性差を理論の土台としておられるわけです。
男性脳と女性脳の性差を過大に見積るべからず
私も、右脳・左脳理論とは違って、身体に差がある以上、脳に性差があってもそれは自然なことと考えながらも、この点に関してはまだまだ未解明な部分が多いと認識しておりましたし、そもそも心理学者の言、特に脳に関する言は私の中では信頼度はかなり低いですので、話半分としています。
私がよく参考にし、また自身の経験知の理論的拠り所としています池谷裕二博士は、「現段階では脳の性差は思うほどは大きくない」という結論のようですし、神経科学分野(俗に言う「脳科学」の主たる分野)では最も真摯な研究を行われている藤田一郎博士の研究室では、空間認知能力の性差について学生たちが次のようにまとめていました。
空間認知能力には何らかの男女差が見られると考えられるが、結果もまちまちであり、性差を結論付けるにはテスト自体やテスト条件に孕む問題をもクリアーに補正していかねばならない。
藤田博士の研究室ならではの実にフランクな分析ですね。
要するに、ぶっちゃけ脳の性差に関しては本当のところはまだまだ分かっていないし、巷で男性脳だの女性脳だのと軽々しく持ち上げられるほど大きな性差はないだろうというところに落ち着きそうです。
スチーヴ・ビダルフ氏は私より一つ年上という年代でもあり、最新の神経科学の研究以前の古きコンセンサスに依拠されていたでしょうから仕方のないことなのですが、読み手の私たちはその辺りは補正して読むことが必要になります。
さらに2015年には、男性と女性の脳には性差はないという論文が数々と発表されるに至っていますから、男性脳・女性脳といった一般受けする物言いは商業主義の化身と考えておくことが無難です。
The human hippocampus is not sexually-dimorphic: Meta-analysis of structural MRI volumes
The brains of men and women aren’t really that different, study finds
所謂『脳科学者』においては、論文を一つも書かないで、裏を表だと洗脳するような方も居られますし、脳に近い専門とは言えるけれども、実は都合のよいように利用しているに過ぎない方も居られますから、ともかくも一定の精査をして参考にするしないを判断する姿勢は持ちたいものです。
とは言っても、こういったことを頭の片隅に置かれてさえいれば、『男の子って、どうしてこうなの?』を読まれてみることはおすすめです。
子どもは保護者だけによって育つのではない
この記事を書きましたのも、その理由の一つとして、『保護者の教科書』(第2版:保護者18切符)でもしたためた「子どもは保護者だけによって育つのではない」という部分を象徴するお話がありましたのでご紹介しようと思った次第です。
そのお話というのは、ネイティブ・アメリカンであるラコタ族の興味深いイニシエーション(少年から大人への通過儀式)のお話です。
アメリカ・インディアンと言えば、私などはちょうど大学受験の頃の事件でもあり合格後にも評論雑誌でその事実を知ったウンデッドニーの二度にわたる悲劇を思い出すのですが、まさにその悲劇の主人公となった部族のお話です。
ラコタ族の男の子は14歳頃になると、大人になるために一つのイニシエーションをクリアーしなければなりません。
先ずは、「ヴィジョン・クエスト」という儀式が待ち受けています。
山の頂上に座って断食をし、飢えによってヴィジョンや幻覚がもたらされるのを待つというものです。
この儀式を無事にクリアーすると部族の元に帰って、試練に耐えたということで祝福されるのですが、面白いのは、その後2年間、母親との会話を禁じられるということです。
イニシエーション(儀式)を受けて男になった少年がその直後に母親と話をすれば、少年時代に戻りたいという欲求が高じ、女性の世界に後戻りして成長しなくなる、とラコタ族の人々は考えていることによるそうです。
子どもたちはしばしば女性の小屋やテントで、女性の傍らで眠り、2年間が過ぎると、母親と息子を再び結びつけるための儀式がとり行われます。
しかし、その時には少年は一人前の男になっており、母親と対等な関係を結ぶことができるのです。
この話をセラピーの中で男の子をもつお母さんにすると、しばしば大きな感動を呼ぶことがあります。
お母さんたちは、悲しみと喜びの両方の感情を覚えるようです。
ラコタ族の母親は、息子を手放すことによって、息子が尊敬すべき大人の友人として戻ってくるのを保証されるのだということです。
如何でしょうか?
おそらく、何と野蛮なイニシエーションだと思われた方も多いのではないでしょうか?
私としては、こういったスピリチュアルなイニシエーションを信じているわけでも推奨しているわけでもありませんが、一定期間母親との接触を禁止されるという慣習の中に、野蛮を超えた知恵の中身を汲み取りたいと思うわけです。
ともあれ、お母さん方には「とんでもないことだ」と嫌われそうですね。
スチーヴ・ビダルフ氏はテストステロンの調整という視座から男の子の教育を見られているわけですが、男の子に限らず、この視座にはなるほどと思えるところを感じますし一定の科学性もあると考えています。
このお話は、今では「死ことわざ」かもしれませんが、私の幼い頃に母親がよく言っていた言葉に『獅子は我が子を千尋の谷に突き落とす』や『若い頃の苦労は買ってでもしろ』ということわざにも通ずるところがあります。
今となれば、
「厳しいのはいいけど、子どもにそれを言っちゃ興ざめでしょ」って話ですが…(笑)
共通するのは、無理矢理、子どもにとって辛いことを問答無用に義務として課してしまうということに集約されるのではないでしょうか?
ラコタ族の母親にとっても内心は辛いことであるでしょうし(彼女たちが如何にそれを受け入れているのかは当人に聞かないことにはわかりませんが)、日本の母親にとっては「心を鬼にして」あるいは「心で泣いて」そういう試練を受け入れたり主体的にやってきたのではないかと思うのです。
とにかく最近は、「好きなことをやる」「自分らしく」ということが強調されますから、ともすれば「嫌なことはやらなくていい」「他人のことは知らない」といった極めて個人主義的な態度にすり替えられがちになってしまっている傾向は否めません。
もちろん、それぞれの子が人生の主人公になるべきですし、ならなくちゃいけない。
だからといって、子どもの顔色だけ伺って、好きなようにさせていていいわけがありませんよね。
しかし、「こんなに過保護に育てられてこの子は将来どんな大人になるのだろうか?」と恐ろしくなる場面が日常的に感じられることがあまりにも多い気がするのです。
過保護の話は別として、思春期に差し掛かる頃のお子さんが言うことを聞かないとか、成績が落ちて来たというご相談が多い中で、せっかく家庭教師を付け、水泳やスポーツ教室にも行ったりしているのだから、良き方向に導くように親戚の方や家庭教師やインストラクターに子育てに関する応援をお願いし、その根回しのストーリーをこのように考えてみてはどうかというアドバイスをさせていただいても、どうも気に入らない方もチラホラ見受けられるのは残念なことです。
あまり他人には頼りたくないという気持ちが大きいのでしょうか?
あるいは、そこまでするのは煩わしいという心理なのでしょうか?
我が子を千尋の谷に突き落とすとまではいかなくとも、少なくとも思春期に差し掛かる頃には、親ではなく書籍をも含めた第三者から学ばせるということをもっともっと積極的に採り入れるべきだと考えるわけです。
親が子どものペースに合わせているのであれば、なおさら世間の風に当たることが必要ではないでしょうか?
世間といっても、下世話な世間ではなく、お子さんの健全な成長を真剣に応援してくれるであろう世間です。
ラコタ族の男の子が14歳頃に大人になる儀式を受けるということは、思春期に差し掛かる子どもは本来的に親から離れ、社会から学んで自分を確立していこうとする時期であることを暗黙知として見抜いているかのような慣習だと考えずにはいられません。
私は、15歳前後が人生最大の重要な時期だと耳タコで書いていますが、この時期を自身にとっても社会にとって実りのある結果に導くのは、ラコタ族のような強制的なイニシエーションがない限りは、そこに至るまでの子どもを取り巻く環境によってしか決定づけられないということを暗に含んでいます。
だからこそ、保護者は全て自分で立派に育て上げるなどと鼻息を荒くするのではなく、良い影響を与えてくれそうな取り巻きに応援してもらうという発想が、とても重要なことだと思うのです。
『男の子の成長には3つの段階がある』という冒頭の章は、私が学習段階を3つの段階に分けたことと概ね対応しているのですが、私たちにとって最も悩みの種である14歳以降の第3段階に書かれている内容は、現代の私たちにとって非常に示唆深いものです。
さらに何度も繰り返して申し訳ないのですが、15歳前後というのは、人間形成面でも学力面でも、その方向性を決定づけてしまう大転換期であり、だからこそ「反抗期」の結論がそのまま表れてくるのだとも言えます。
【少年・少女から大人になる節目】に対する親の気持ちの節目が年々喪失されつつあるように思えてなりません。
この部分だけでも一つの著作を書かなければならないほど重要なことですが、今はビダルフ氏の次の言葉として結論しておきましょう。
親は、信頼のおける他の大人たちの長期にわたる積極的な助けがなければ、十代の少年たちを育てることはできない。
男の子らしく育ってほしい!?女の子らしく育ってほしい!?
ご紹介した本のタイトルからすれば、このことが主題になるはずなのに、最初に「男性脳と女性脳の性差」のことを少し述べただけでした。
それも、「過大に見積るべからず」という素っ気ない結論だけでした。
しかし、現実には男の子だからというご相談や「男の子らしく育てたい」といった願いには、ほとんど出会ったことがなく、むしろ「女の子らしく育ってほしい」「女性であることに自信をもって育ってほしい」という言葉や決意には、結構多く出会いました。
男の子は、もはや、あまり期待も重宝もされていないんでしょうかね?(笑)
実は、このことは社会の大きな問題の現れなんですが、それは要らぬおせっかいとして野暮なことは述べないことにしましょう。
さて、先のような呟きに出会ったとき、私自身は、日常会話的に次のようにお答えします。
「あまりそういうこと考えない方が普通に育ちますよ!」
思わせぶりに終始して申し訳ありませんが、それが私自身の結論です。
さて、私は、学習方法論における『ひらめき』の正体を暴いた後は、『やる気』『本気』の本丸から『学び』全体の構造を子育てと学習方法論の体系化としてまとめていきたいと考えています。
その結実が、現在【帝都大学へのビジョン】の別冊2としております「保護者18切符」です。
本編と別冊2「保護者18切符」は単品販売もご用意しておりますので、興味があられたらご一読くださいませ。
勉強の仕方の本質を起点としていますので、ある意味これだけですべてをが手に入れることができちゃいます。