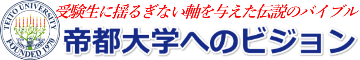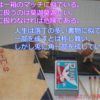Bクラスを目指すべき中間層が居なくなった?
今回は、花森安治氏の「自分の手で、爪に血をしたたらせて、こじあける」をご紹介した記事において河盛好蔵氏のエッセイ『Bクラスの弁』をご紹介すると予告しておりましたのでご紹介しておこうかと思います。
ここに記したコンテンツは、「爪に血をしたたらせて、こじあける」とか「精神に汗をかけ」いった主体としての心構えだけではありません。
「凡庸だけれども一生懸命努力している学生」こそ大切にしたいという指導者側の思いや願いから認められた文章です。
そういう意味では、厳しさでなく深いやさしさを背景にした筆ですから、その願いを汲み取り、ここを自分の人生の出発点に据えていただければと願います。
松平先生が言われるように「努力する能力も学生が身に着けるべき大切な資質」だということを自分の人生をよりよく生きるためには欠かせないことだを感じていただければと願います。
「要旨フロー」に出てくる一つ一つの言葉は、実に深い箴言となって返ってくることでしょう。

何故、紹介したかったのかという動機ですが、ここ10年ほどの間でしょうか、Bクラスの存在自体が空洞化してしまう危機感が非常に強くなったということにあります。
学力の2極化は誰しもが感じるところとなっていたわけですが、その2極化の具合があまりにも尖鋭となって、社会の根幹を成すべき最も重要な中間層が不在になってしまう危惧を感じてしまうほどになってしまったと感じるのです。
というか、むしろ努力もせずに気持ちだけで妙な自信をもって自分をAクラスだと思いこむ人々が増えてきたように思えることが気がかりです。
極端に言えば、「勉強などできない奴の方が社会では優秀なんだ」という雰囲気を根拠に、勉強などできない自分の方が役に立つ人間だと短絡的に合理化したり、マスコミに出てくるレベルの評論家(当然、社会現象に関する感想や推測レベルの無責任なおしゃべり)を対戦相手にして自分も対等に語り合えたり批判すらできる優秀な人間だと錯覚したりします。
「君たちはどう生きるか」で、おじさんがコペル君に語ったように「分際をわきまえる」ということの意味や本質を考える機会を与えられず、ただただ「君も世界に一つしかない花だよ」と甘い言葉だけにしか接してこなかったとなると、これは、やはり人間としての全面的成長には大きな落とし穴があるのではないかということを少し考えてもらえれば嬉しいと思います。
『Bクラスの弁』は、今ではどこに収められているのかは定かではありませんでしたので調べてみますと、どうやら『私の人生案内 (河盛好蔵 私の随想選) 』に収録されているようです。
それほど長くないエッセイなのですが、それでも一部の引用だけでは概要を掴むことは難しいですので、先に河盛好蔵氏がフランス文学者であったこと及び大筋の流れをリストアップしておこうかと考えます。
故河盛好蔵氏は働き盛りの30代を立教大学の教授としてフランス語を教えられており、その時の学生との関り体験から生まれた随想が、この『Bクラスの弁』だと思われます。
『Bクラスの弁』の要旨フロー
- 私は久しく某私立大学の教師をしていた
- 入学試験の口頭面接で、官学の入試に失敗してやって来た諸君は概して態度が傲慢で、こんな学校には本当は入りたくないけれど兵隊にとられるよりはマシだから腰掛けだよオーラが露骨
- 最初から、本大学を志して来たれり諸君は何としてでも入学を許して頂きたいという熱望に眼を輝かせている
- 入学を許されると、官学入試失敗者はつまらなさそうに同級生をバカにした日々を送り、志で来たれり者は学校の空気に溶け込み、それなりに勉強し、ちゃんとした会社に就職し、立派に社会人として活躍
- 教室における出来栄えは、もちろん官学入試失敗者の方が優れている
- 教師は自分の学科をよく勉強しさえしてくれれば評価してしまうもので、私も当初は例外ではなく、それが学校の質の向上にも繋がると考えていた
- 自分ほどの能力の教師はこんな学校にはもったいないと自惚れていたことも要因としてあった
- しかし、長い間に自分の考えの至らなさに次第に気付き、自分の分に甘んじて、その場限りにおいてよくやっている凡庸な学生をこそ大切にしなければならないと悟った
- 世の中は、指導者にもなれず大して出世もしないであろうが、自己の権勢欲のために他人を犠牲にしたり悪事を企んだり進んでは国を売ったりすることがないであろう彼等によって支えられている
- 今度の戦争(大東亜戦争)を引き起こした元兇たちを詳しく調べてみるならば、いわゆる天下の秀才たちがその有力な分子をなしていることに人は驚くに違いない。
- 私自身がBクラスに属すること、その自覚のもとに生きなければならないことを悟った。
- 決して、自分を卑下したり過小評価することが趣味になったわけではなく、実力のあるBクラスになることはAクラスのエピゴーネン(亜流)になるより遥かにむつかしいこと
- 自分はもとより欠点だらけの人間だが、努力することなく、他人の長所・美点を虚心に認め、これに素直に感動する恵まれた性質を具えていることに幸福を感じている
- 他人の才能を素直に認めることは私にとって何もマイナスに作用することはなく、むしろAクラスのエピゴーネンになる愚かさから逃れ、Bクラスとしての存在を確立させようと自覚させてくれた立役者
- 世間の常識はBクラスはAクラスより一段程度の低いものとなっている
- この常識を一応は承認するが、私の考える「精神の世界」では、Bクラスも勉強すればAクラスになり得るというものではなく、Aクラスも怠ければBクラスに転落するという種のものではない
- Bクラスの人とは、ヴァレリーがデカルトの親友であったメルセーヌ神父について著した如く、その仕事の中に更に高次の才能を生む養いが含まれているような人である
Bクラスを目指すという分際、Bクラスとしての矜持
Bクラスなみに完成することに彼等の存在の意味があるのではない。
Aクラスに至る道を作り、その地盤を用意する点に、彼らの使命があるのである
私たちが記した資料『天才ボーアを閃かせたバルマー先生』においてお分かりいただけたと思うのですが、中学の教師だったバルマー先生も天才ボーアが至る道を作ったと言えます。
近代物理の画期的な成果だった『量子論』は黒体放射のスペクトル等から始まり、それ自体がAクラスと思える叡智の集合体と言えますが、それぞれの叡智の中にはそれを支える叡智が入れ子のように重なっていることは勉強していかれれば、つくづくと感じていかれることでしょう。
資料『天才ボーアを閃かせたバルマー先生』はバルマー先生が歩んだであろう道の周辺は、高校1~2年生の数学レベルで結論を導き出せるところまで散策することが楽しめるユニークな資料です。
(資料類はすべて、『帝都大学へのビジョン』ALLコースに付属しております)
但し、一般公開は終了していますので、学校や塾をはじめ、世間では決して教えてくれないような二次関数の利用の仕方や類推力を本資料で体得していただけると思います。
(「いいね」の数が少ないのは、公開終了後しばらくしてから、当サイトのURLを公式サイト下に移転したためです。)
Bクラスとしての職分を忠実に行なうためには、常にAクラスの英才たちの仕事とその努力から目を離してはいけない。
<中略>
これは彼等のあとに追随するためではなく、彼等と私たちの間の距離を正確に知っておくためである。
オスカー・ワイルドの言葉に『想像力は模倣する。創造するのは批判的精神である』というのがあるが、わが国には自己の能力と他人の才能に対する正しい判断や評価を欠いて、いたずらにAクラスの世界の雰囲気にあこがれ、模造品を作るのが関の山で、のみならず、真の天才の出現を妨げている連中があまりにも多すぎるのではないか。
私は教育者とジャーナリズムの仕事は、言葉の最もすぐれた意味におけるBクラスの人々の仕事ではないかと思う。
それは世の秀才たちに彼等の才能をあますところなく発揮させるためにあらゆる奉仕を厭ってはならないということである。
しかし、世の教育家やジャーナリストたちに・・・。(この部分は読者のご想像に委ねましょう)
『帝都大学へのビジョン』を執筆した私たちも、実にこの気持ちが強いことをお伝えしておきたいと思います。
私たちはAクラスの人間ではありませんから、何とかBクラスの人間として最高の仕事をしたいと励んできましたし、縁あって教育にもこのような形で関わる中では、やはりAクラスの人間を輩出していきたいですが、より一般的・現実的には、何よりもBクラスとしての務めを黙々とこなせる人材に育ってほしいということが大切な目標としてあります。
このエッセイの要旨だけでは物足りないと思いますが、その真意を汲み取ることはできると思いますので、これを読んでいただいた受験生諸君には、大いにBクラスの精神を目指して、実りある人生にして頂きたいと願うのみです。
学力だけが優れた人たちとそれを嘲笑う人たち
「Bクラスの弁」で出てくる「官学の入試に失敗してやって来た諸君」のように鼻持ちならない人は、官学に合格した諸君の中にも少なからず見かけると思います。
下品な言葉で言ってしまえば、彼らは鼻くそのような人たちです。(エラそうにしている時点で人格的にもですが、えてして能力的にも大したことがないものです)
とてもAクラスだとは言えないだけでなく、Bクラスになれる器も持たない人たちです。(不思議ですね!)
しかし、だからと言って、君たちが自分は何の努力もせずに彼らを嘲笑うことに快感を覚えているだけなのであれば、君を評定する人の目には「目くそ鼻くそを笑う」と映ってしまっていることだけは忘れないでください。
学歴だけで一流組織に入ったとしても、(組織の尺度で)使えない人材は自然に淘汰されていくのと同様に、自分が何にも努力せずに嘲笑っているだけなのであれば、最初から彼らと同じスタートラインに立てることすら叶わないのではないでしょうか?